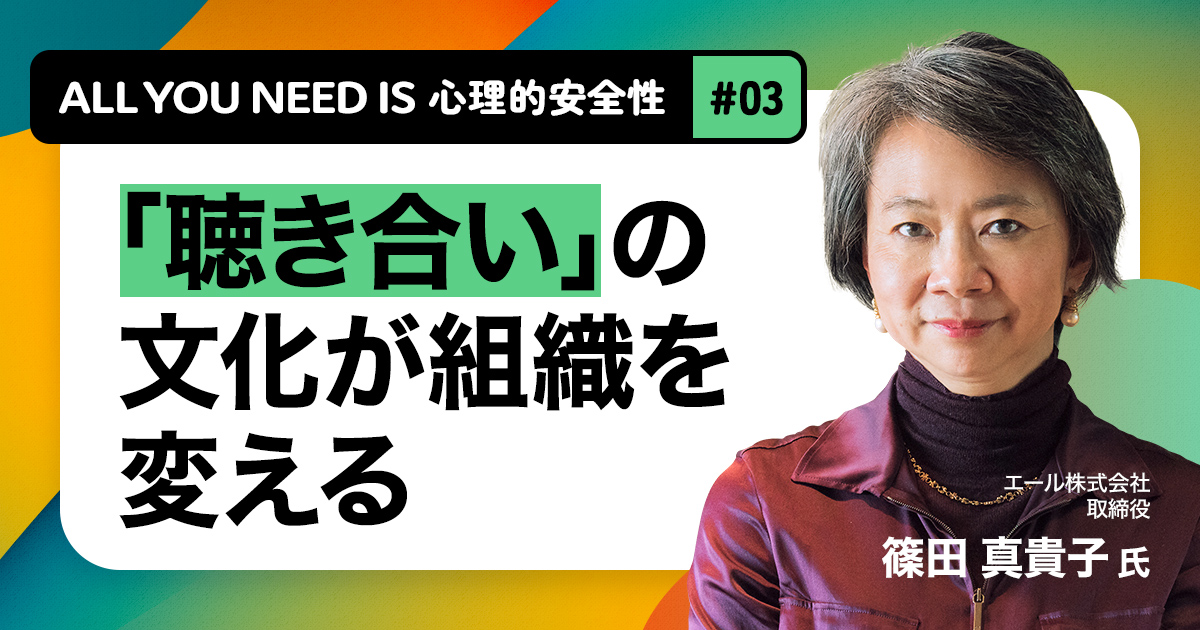DeNAに聞く「会社から信頼される人事」になるための心構え
2023.10.04
今、経営者のビジネスパートナーとして、人事領域から事業成長をサポートする「HRBP」(Human Resource Business Partner)を導入する企業が増えつつある。
事業拡大に奔走する最前線に身を置き、「経営」と「人事」という二つの目線から、組織改革を行うHRBP。株式会社ディー・エヌ・エー(以下DeNA)では2014年にHRBPを各事業部へいち早く導入し、現場の生の声を人事戦略に反映させてきた。
しかし「経営にコミットするまでには長い道のりがあった」と、HRBP設立の初期段階から組織開発に携わっている現ヒューマンリソース本部・本部長 菅原啓太氏は振り返る。
文字通り事業成長の「ビジネスパートナー」として、経営にコミットできるような人事になるためには、どういったことを意識し行動すればいいのだろうか。
また、HRBPを束ねるリーダーとして、心がけるべきこととは?菅原氏に、ノウハウを伺った。
Profile

菅原 啓太氏
株式会社ディー・エヌ・エー/グループエクゼクティブ ヒューマンリソース本部本部長
IT系ベンチャー企業での勤務を経て、2009年にエンジニアとしてDeNAに入社。Mobageの事業責任者や新規事業の立ち上げを経験した後、2015年から人事領域へ。2017年からゲーム・エンターテインメント事業本部の組織開発部 部長 兼 HRBPを経て、2020年4月より現職。30年来のベイスターズファン。
多角化に伴い生まれたHRBPという役割
―まず、菅原さんご自身は日本企業の人事を取り巻く環境について、現状をどのように捉えていらっしゃいますか?
2020年9月に発表された「人材版伊藤レポート」で人的資本経営のあり方がまとめられ、予測困難な現代社会における人材戦略が見直されたことで、日本国内の企業には一層「人が事業の主役である」という考え方が普及するようになりましたよね。
そもそもこの「人的資本経営」という概念が浸透した背景には、消費の変化が深く関係しています。
たとえば「どれだけ効率よく同じものを大量生産すべきか」が重視されていた時代は、モノやサービスを扱う「事業」がビジネスの中心でした。事業を稼働させるために人を雇う、という考え方が主流だったと思います。

そこから徐々にエンドユーザーのニーズが多様化することで「何を作ればいいか」が曖昧な時代に突入しました。今や人々の求めているモノやサービスは目まぐるしく変化し、多岐にわたります。
競争に生き残るためには「事業」ありきではなく、ニーズをキャッチして事業に反映させる「人」ありきの組織に変えていかなければならない。そして個々の人材のスキルを発揮するための人事戦略が重要になる。ここ2〜3年で、経営者も気づき始めました。
「人事こそが事業の要である」という認識が広がり始めたからこそ、我々人事にとっては面白いフェーズに突入していると感じます。
―DeNAでは社会の変化に対し、どのように人事組織を変化させてきたのでしょうか。
ゲーム事業とスポーツ事業を主軸に経営を続けていた2010年代は、人材配置から育成、組織開発までの業務をHR部門で一元管理していました。
そのうちライブストリーミングやヘルスケア、オートモーティブ事業など、事業も多角化。幅広く事業領域を拡大していき、事業ポートフォリオが進化していくほど、求める人材の幅も広がっていきました。
一方、事業ごとにビジネスモデルも違えば、必要とされる人材の特性、さらに言えば発生する課題も多岐に及びます。一元的に人事戦略を運営し、組織開発を続けることに限界が見えてきました。
人材ポートフォリオを組み替えていき、スキルセットの異なる人たちを包摂できる環境づくりを進めるには、各事業部の現場から発生する生の声を聞かなければいけません。
そこで、DeNAでは現場の社員の声を聞きながら、イシューを根本的に解決すべく2014年に事業部ごとの人事戦略を担うHRBPが設置されました。
「人」という資本のもつスキルを最大限に発揮するために、事業と人事、そして経営を繋ぐ部門としてHRBPを機能させ、事業ごとに制度や人事開発を柔軟に組み替えていく戦略を取るようになったのです。
―DeNAにおいて、具体的にはどのようにHRBPが機能しているのでしょうか。
まず、労務や給与計算、新卒採用全般といった全社共通の人事的な役割を司るHR本部があり、ゲーム・エンタメ事業やライブストリーミング事業、ヘルスケア・メディカル事業といった各事業部ごとにHRBPがいる構造です。HRBPの多くはHR本部に所属していますが、事業部直属のHRBPがいる組織もあります。
先ほどもお伝えしたように、人事戦略課題は、事業に応じて全くバラバラ。ゲーム・エンタメ事業のHRBPとスポーツ事業のHRBPでは、全然やることが違うんですよ。

ただ、どの事業部を担当するにせよ、HRBPは人事・組織周りのイシュー全般――ネクストリーダーの育成から採用、評価軸の整理から目標設定まで、幅広い業務を担っています。
各事業部が抱える課題を人事的な観点から解決し、事業が成長するための環境を整えることが主な役割です。
私自身はエンジニアとして2009年に入社後、ゲーム・エンタメ事業で新規事業の立ち上げなどを経験しました。その後、2015年にHR部門へ異動。前年に立ち上がったHRBPとして、まずはゲーム・エンタメ事業の人事戦略に携わるようになります。
「人事」が事業戦略にコミットするための3STEP
―DeNAのように事業部内にHRBPを設置する企業は増えつつあります。HRBPとしての役割を果たすためには、どういった心構えが重要なのでしょうか。
肩書きは「人事」の人間でありながらも、最終的には「人事組織面での各事業リーダーのパートナー」として戦略・施策の実行まで深く介入することが求められる存在。まずはHRBPの役割について、そう自覚することが重要です。
ただ、社内で「組織の課題解決ができる人材」としてのポジションを確立させるまでには、とても時間がかかります。
実際、私がHR部門に異動した当初、事業拡大のための人員計画や採用計画にまつわる事業部内の話し合いに、HR部門って参加できなかったんですよ。
HR部門にとって「事業を伸ばすために何人採用したい」という情報も、各事業部からトップダウンで降ってくるもの。それくらい、各事業部の立場が強かったです。人員計画の立案に参加できるようになったのも、HRBPが導入されてからでした。
おそらく、事業部の立場からしても最初は「HRBPって何をしてくれるの?」という「謎の役割」であったはず。だからこそ、事業部にとって真の「ビジネスパートナー」になるためにも3つの段階を踏むことが重要でした。

まず、最初は「HRGK(HRの御用聞き)」、つまり事業部から言われた人事タスクをこなす存在として、期待に応えられるよう行動することです。私自身、HRBPとしてゲーム・エンタメ事業に配置されて最初の1年は、組織のことでできることがないかを聞き、淡々と期待に応えていくだけでした。
そのうち「こういう球も拾っていけるのか」と思ってもらえるようになると、次のステップである「HRPP(HRピープルパートナー)」へと昇格。事業部から課題ベースで人事領域の相談をしてもらえるようになります。
そしてHRPPとしてイシューを解決していくうちに、事業部長や事業部内のグループリーダーにも話を聞いてもらえるようになり、経営視点で具体的なHR領域の提案ができるようになる。ここで初めて「HRBP(HRビジネスパートナー)」を名乗れるようになります。
―HRBPとして行動できるようになるまでに段階を踏み、信頼を勝ち取らなければならないのですね。
むしろそのステップを踏まないと、いつまでも「人事部門から来た謎多き役割の人」のままだと思います。
特に私は人事としてのバックグラウンドがなく、社内でもHRBPが立ち上がって1年も満たないときに、ゲーム事業のHRBPに就いたんです。何をすべきかが決まっていない状態だったからこそ、率先して段階を踏み、事業部の信頼を得ることが必要不可欠でした。
これからHRBPを新設する場合、いきなり評価制度などの領域に足を突っ込むと、むしろ事業部にとっての「敵」になってしまう。なおのことステップを経た方が、スムーズだと思います。
真の「HRBP」を目指すために重要なアクション
―HRGKからHRPP、HRBPへとスムースに昇格していくためには、どういった心構えが必要なのでしょうか。
まずHRGKからHRPPになるためには、「HRが主導権を持ちやすい領域で勝負すること」が重要です。具体的には採用や配置、マネジメント強化などが、HRの主導権を持ちやすい領域。そこでプロフェッショナルとして認めてもらうことで、パートナーシップを築くことができるようになります。
たとえば私の場合、配属された当初はHRGKとして、求人票の作成やグループ会社への出向手続きなど、あくまで「事業リーダーのタスクをサポートする役割」をこなしていました。ただ、それだけだとずっとHRBPにはなれないと感じていたんです。
事業の動きを観察しているうちに、ゲームクリエイター不足が事業のボトルネックになっていて、新規開発をやろうにも着手できない状況であると感じました。
同時に気づいたのは「退職を抑止すること」も急務であるということ。
そこで、事業部のエンジニア100人にヒアリングを行い、現場の悩みや不満を抽出する役割に徹してみたんです。また、事業部内のマネージャーが当時4人いたので、それぞれに話を聞きに行って。
すると、100人の組織をたった4人でマネジメントしていたので、現場から上がってきた「マネージャーと話せない」「開発方針がわからない」「悩み相談ができない」という声も理解できました。
ヒアリングから分かったことをまとめ、マネージャーとしてポテンシャルのあるメンバーの具体名を挙げながら、事業部リーダーにマネージャーを増やすことを提案。2017年はゲーム・エンタメ事業だけでも離職率は最大18%と非常に高かったなか、半年間の組織開発を経て一桁台まで離職率を下げることに成功しました。

―人事の専門性を活かした提案を行うことで、まずは信頼関係の土台を構築するということですね。では、HRPPからHRBPになるためにはどういったアクションが重要でしょうか。
「経営戦略や事業戦略を変革するためにはこういうことをすべき」と状況を先回りし、HR施策を提案することが求められます。事実、各事業部のHRBP同士で裏を取りながら、未来を見通してアクションを起こすことで、事業の計画立案から携われるようになりました。
M&Aを締結する際、デューデリジェンスの段階から入らせてもらえるようになったりと、事業の経営戦略に、深くコミットできるようになったのは、逆算しながら連続でバリューを出すことを意識し始めてからでした。
ただ、そのためには経営や事業、戦略などの情報をインプットし続けることが重要。HR本部として、部門のメンバーには「人事」だけではなく「経営」のプロとしての意識を持ってもらうことを意識しています。
HRBPを担う人材には、事業の経営情報をとにかく詰め込んでもらっていて。「情報からどういった見通しを立てられるか」を日常的に予測・ディスカッションしてもらい「先を見通す能力」を鍛えてもらうようにしています。

ただ現場における人事担当者の「先を見通す能力」を鍛え、段階ごとにスキルセットを行うことは、HRBPを抱える人事トップだけに求められるタスクではないと思うんです。
社会全体でも「人」が事業の主役になりつつある現在。人事が主権を取り戻す良い流れは生まれています。経営陣にいながら戦略人事を実行するポジションであるCHRO(最高人事責任者)のニーズが高まっているのも、経営と人事を地続きに捉えるようになった良い傾向です。
ただ、経営陣がその役割を担わなければいけないというのは、「人事と経営の両方の目線を持つ人材が少ない」ことの顕れだとも思っています。
今後、経営と人事がお互いに歩み寄っていく流れは加速していくはず。経営戦略と人事戦略をつなぎこむような施策がどんどん生まれることで、今までは実現しえなかったような「大きな変化」がどんどん生まれるチャンスがあるんです。
そのチャンスを掴みとるためにも、人事トップは、自分を「人事マン」であるとは捉えず、柔軟に行動すべきだと思います。そして「人事として今後どういった知識や能力が求められるか」を先回りすることが、最終的に企業の成長に繋がっていくはずです。
―新たな戦略の成功可能性を高めていくために、人事トップはどういったことを心がけるべきでしょうか。
戦略を進めていくなかで、一度「その戦略は会社のカルチャーを維持できるか」という視点を挟むことが重要だと思います。
もちろん人事戦略に限らず、あらゆる戦略は企業のカルチャーに根付いて生まれると思うんです。「カルチャーと紐付けなければ」と変に意識してなくても、必ず反映されている。そう言っても過言ではありません。
しかし、時代の変化に合わせて自分の役割が刻一刻と変化していくと、会社が長い年月をかけて築いてきた「大事にすべき価値観」を見失いかけることもあります。
脈々と受け継がれてきた大事なカルチャーを維持・保存していく。そのためには人事戦略を進めていくなかで俯瞰的な目線をもち「この戦略は会社のカルチャーにマッチしているのか」と立ち止まる時間が必要なんです。
ちなみに、私自身はDeNAが最も大事にしているカルチャーを「『こと』に向かう」だと思っています。
「『こと』に向かう」とは、企業の行動指針である「DeNA Quality」の一番上にバーン!と提示されている言葉。本質的な価値の提供に集中するという、我々が事業を展開するうえでの重要な考え方です。エンドユーザーにとって本質的に価値があるものを届け、あくまで対価としてお金をいただく……という、我々が事業を展開するうえでの重要な考え方です。

この言葉の対になるのは「『人』に向かう」ということ。つまり、上司の顔色やビジネス的な利益だけを考え、事業を展開してしまうような行動を指します。
どれだけDeNAが裾野を広げ、1万人規模の会社になったとしても、「『人』に向かう」ような社内環境は作りたくない。誰もが「『こと』に向かう」ことのできる環境づくりこそが、DeNAという企業を成長させるための鍵になるんです。
社員一人ひとりの変革や挑戦を支援し、フラットな「永久ベンチャー」の組織であり続けるためにも、根幹はブレないよう俯瞰しながら調整をしていく。これが、DeNAのHR全体を見守る私自身に求められる役割だと考えています。
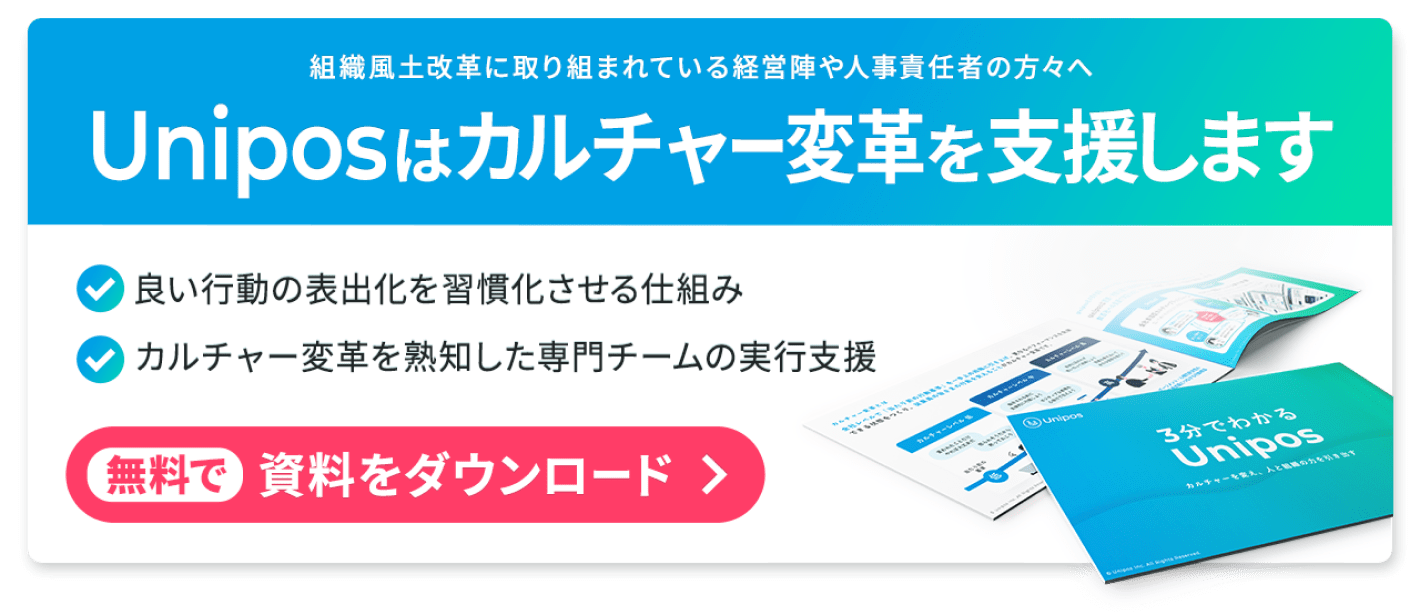
この連載の記事一覧